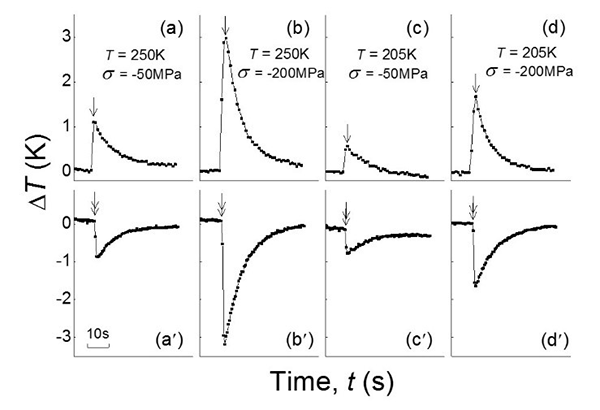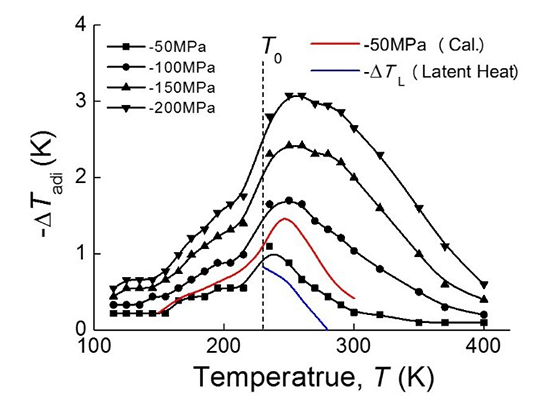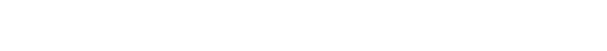| 実績概要 |
<H26年度>
第一原理太陽電池材料シミュレーターの基礎的な開発を行った。古典的なShockley-Queis ser(SQ)理論では、太陽電池の変換効率を(1)単一pn接合、(2)簡単化した光吸収係数、(3)電子-正孔の急速な熱緩和、(4)非輻射再結合過程の無視、を前提としているが、今年度はまず(2)について第一原理による光吸収係数を効率計算に取り入れた。?VASPパッケージに実装されたHybrid法を用いて半導体の光吸収係数を計算し、古典的なShockley-Queisser(SQ)理論をベースとする効率計算プログラムに組み込み現実的な効率限界を計算できるようにした。環境調和性が高い半導体系(例えば、SnS, Cu2O, FeS2, Zn3P2, Cu2S, Cu3N, Sb2S3, Bi2S3, Fe2O3, WSe2,MoS2, Co3O4, WO3, ZnSn(N, P)2, Cu2SnS3, Cu4SnS4, Fe2(Si, Ge)S4, CuSbS2, Cu2ZnSnS4など)について効率の計算を行い太陽電池材料としての性能を評価した。 光学特性の計算に用いたHybrid法(HSE06法)は高精度の光学特性計算法として知られているが、本研究によりFeカルコゲナイド系 についてはバンドギャップの予測能力が十分でないことが明らかになった。さらに高精度な光吸収係数の計算法として小谷(鳥取大) によるQSGW法を用いることを検討し、試行的な計算として近年実験的に合成されたbeta-CuGaO2の光学特性を評価した。
<H27年度>
古典的なShockley-Queisser(SQ)理論を光吸収係数の第一原理計算と組み合わせ、現実的な物質パラメーターを用いたエネルギー変換効率のシミュレーターの開発を継続した。これまでに電子状態および光吸収係数の計算に用いてきたハイブリッド法に加えてさらに高精度な計算法であるQuasi-particle self-consistent GW (QSGW)法を用いた計算を系統的に行い、しみレータとしての有用性を確認した。具体的には50種類程度の半導体や酸化物の系にQSGW法を適用し、バンドギャップエネルギー、バンド構造、有効質量など太陽電池特性を左右する物性パラメーターをどの程度再現できるかを調べた。その結果、QSGW法は0.2~0.3eV程度バンドギャップエネルギーを系統的に過大評価することが明らかとなり、この過大評価を補正する実用的な方法として、QSGW法にLDAを20%混合する新しいハイブリッド法を太陽電池材料のシミュレーションに使用することを提案した。開発した新しいハイブリッド法を、近年低コスト太陽電池材料として注目されている有機-無機ペロブスカイトやカルコパイライト系太陽電池材料に適用し、タンデム型太陽電池として高効率が期待できる組み合わせを提案した。また、開発中の太陽電池シミュレーターを,酸化物太陽電池材料として合成実験が進みつつある擬ウルツ鉱型CuGaO2について適用し,その太陽電池材料としての可能性を評価した。 |
| 発表論文 |
<H26年度>
- Ordered Defect compounds in CuInSe2 for Photovoltaic Solar Cell Application, K. Sato and H. Katayama- Yoshida, AIP conference Proceedings 1583 (2014) 150-155. (http://doi.org/10.1063/1.4865624)
- Computational nanomaterials design for nanospintronics: Room temperature spintronics applications, H. Katayama-Yoshida, K. Sato, T. Fukushima, A. Masago and M. Seike, “Rare-Earth and Transition Metal Doping of Semiconductor Materials Synthesis, Magnetic Properties and Room Temperature Spintronics” (Eds. I. Ferguson, J. Zavada, V. Dierolf, Elsevier, 2015) 3-42.
<H27年度>
- Spinodal nanodecomposition in semiconductors doped with transition metals, T. Dietl, K. Sato, T. Fukushima, A. Bonanni, M. Jamet, A. Barski, S. Kuroda, M. Tanaka, P. N. Hai,? and H. Katayama-Yoshida, Rev. Mod. Phys. 87 (2015) 1311-1377. (http://doi.org/10.1103/RevModPhys.87.1311)
- Accurate energy bands calculated by the hybrid quasiparticle self-consistent GW method implemented in the ecalj package, D. Deguchi, K. Sato, H. Kino, T. Kotani, Jpn. J. Appl. Phys. 55 (2016) 051201 (8 pages). (http://doi.org/107567/JJAP.55.051201)
|
| 学会発表 |
<H26年度>
- K. Sato and H. Katayama- Yoshida, EfficiencyenhancementinCd(S,Te)photovoltaicsolarcellmaterials byself-organizednano- structures, International conference on physics of semiconductors (ICPS2014) 2014年08月10日~2014 年08月16日Austin Convention Center, Austin, TX, USA
- D. Deguchi, K. Sato, T. Kakeshita and H. Katayama- Yoshida, Computational design of photovoltaic solar cell materials with sustainable elements, International conference on physics of semiconductors (ICPS2014) 2014年08月10日~2014 年08月16日Austin Convention Center, Austin, TX, USA
- D. Deguchi, K. Sato, T.Kotani, H. Katayama- Yoshida and T. Kakeshita, CONVERSION EFFICIENCY OF SUSTAINABLE PHOTOVOLTAIC MATERIALS CALCULATED WITH AB INITIO OPTICAL ABSORPTION COEFFICIEN, The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 2014年11月23日~2014 年11月27日Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan
- S. Emura and K. Sato, NEW CONCEPT OF PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL BASED ON SPONTANEOUS ELECTRIC FIELD IN POLAR SEMICONDUCOTOR, The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 2014年11月23日~2014 年11月27日Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan
- K. Sato, H. Tanaka, T. Fukushima and H. Katayama- Yoshida, SELF- ORGANIZATION OF NANO- STRUCTURES IN SOLAR CELL MATERIALS AND ITS EFFECTS ON THE CONVERSION EFFICIENCY, The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 2014年11月23日~2014 年11月27日Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan
- K. Sato, Computational Materials Design for Semiconductor Spintronics, 14th Japanese- American Frontiers of Science Symposium (招待講演), 2014年12月04日~2014 年12月07日Hotel NewOtani, Tokyo, Japan
- 出口大幹、佐藤和則、掛下知行、小谷岳生、吉田博, HSE06法およびQSGW法による環境調和太陽電池材料の第一原理計算とエネルギー変換効率, 金属学会2014年秋期講演大会, 2014年09月24日~2014 年09月26日名古屋大学東山キャンパス
<H27年度>
- K. Sato, Clustering tendency and change in band structure of (Ga, Mn)As and (In, Mn)As, Uppsala-Osaka mini-workshop on computational materials design (invited) 2015年5月4~5、A研究所、ウプサラ大学、スウェーデン
- V. A. Dinh, K. Sato, T. Kakeshita and H. Katayama-Yoshida, Clustering tendency and change in ferromagnetism in (Ga, Mn)As and (In, Mn)As, International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS2015), 2015年7月27日~31日、アールと大学、エスプー、フィンランド
- D. Deguchi, K. Sato, T. Kotani, H. Katayama-Yoshida and T. kakeshita, Ab initio assessment of sustainable photovoltaic materials, International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS2015), 2015年7月27日~31日、アールと大学、エスプー、フィンランド
- V. A. Dinh, K. Sato, H. Katayama-Yoshida and T. kakeshita, Relation between clustering and electronic structure in (Ga, Mn)As and (In, Mn)As, Psi-k 2015 conference, 2015年9月6~10日、ドネスチア,サンセバスチャン、スペイン
- K. Sato, Computational Nanomaterials Design for spinodal nanotechnology; Design vs. Relization, The 19th SANKEN International and the 14the SANKEN Nanotechnology symposium (invited), 2015年12月7?9日、大阪大学吹田キャンパス
- K. Sato, D. Deguchi, H. Okumura, T. Kotani, T. Kakeshita and H. Katayama-Yoshida, Computational design of photovoltaic solar cell materials based on accurate electronic structure calculations, Workshop on Computational Nano-Materials Design and Realization for energy-Saving and Energy-Creation Materials (Invited), 2016年3月25~26日大阪大学豊中キャンパス
|